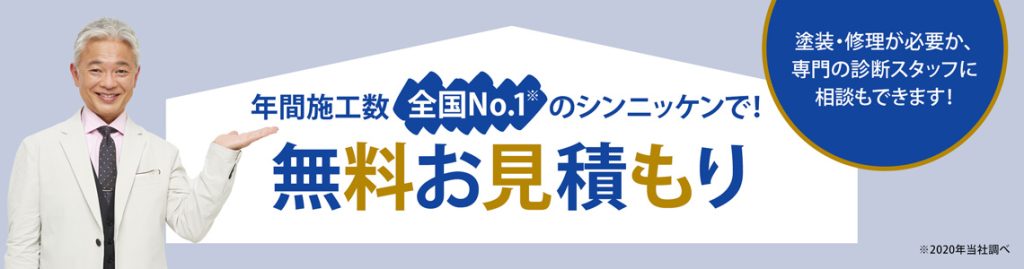外壁塗装の人気色グレー|汚れにくくおしゃれな外観に仕上げるコツ
最終更新 : 2025.05.22

外壁塗装にはさまざまな色がありますが、その中でもグレーは高い人気を誇る定番カラーのひとつです。
落ち着いた印象で景観に調和しやすく、汚れが目立ちにくいといった理由から、多くの住宅で採用されています。
とはいえ、グレーにも色味や組み合わせによって多彩な表情があり、選び方を間違えると「イメージと違った」と後悔することも。
本記事では、外壁塗装でグレーが選ばれる理由から、おすすめの配色パターン、よくある失敗とその対策まで詳しく解説します。
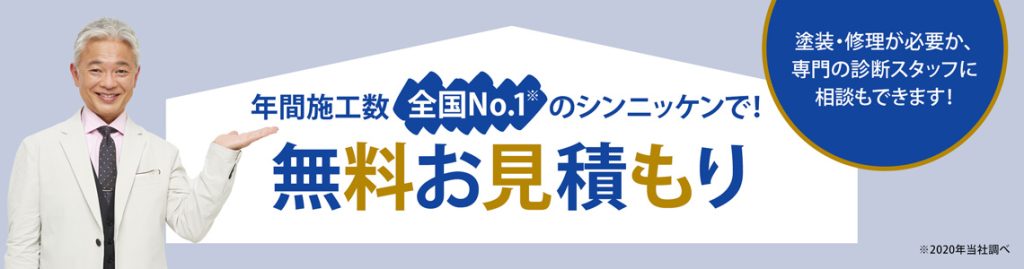
Contents
外壁塗装でグレーが人気の理由

外壁塗装のなかでもグレーが人気なのには、明確な理由があります。
理由を知るだけで、グレーに対する考えかたが変わるはずです。
汚れや劣化が目立ちにくい
外壁につく汚れといえば、排気ガスや土ぼこりなどが代表的です。
これらが外壁に付着すると色味が変化し、くすんで見えてしまいます。
とくに外壁に凹凸があると、汚れがたまりやすく、見た目に影響が出やすくなります。
これらの汚れは「中間色」と呼ばれるグレー系の色が多く、グレーの外壁に汚れがついても、色の差が目立ちにくいです。
また、外壁の劣化のサインとされる「チョーキング現象」も目立ちにくい点が特徴です。
チョーキングとは、塗料の表面に白い粉が出てくる現象で、紫外線によって塗料の樹脂が分解されることで起こります。
指でこすると白い粉がつくため、「白亜現象(はくあげんしょう)」とも呼ばれています。
この白い粉はどの色の塗料でも基本的に白く見えるため、濃い色の外壁では非常に目立ちやすいです。
しかし、グレーはもともと白に近い中間色なので、粉が出てもそれほど目立ちません。
また、劣化による色あせもグレーの場合は変化が少なく、視覚的な印象を損ないにくいという利点があります。
もちろん、実際には劣化していることに変わりはありませんが、他の色に比べて視覚的な影響を抑えられるのが、グレーの大きなメリットといえるでしょう。
シンプルで上品な印象を演出できる
グレーは白と黒の中間に位置する「無彩色(むさいしょく)」で、非常にシンプルな色合いが特徴です。
無彩色とは、色味を持たず明るさ(明度)の違いだけで表現される色のことで、白・黒・グレーがこれに該当します。
グレーはこの無彩色の中でも、中間の明るさにあたるため、主張が強すぎず、外観に落ち着いた印象を与えてくれます。
構成がシンプルなぶん、どんなデザインにもなじみやすく、外壁塗装でも上品で洗練された雰囲気を演出しやすいのが特徴です。
また、グレーには青みがかった寒色系や、赤みを帯びた暖色系など、わずかな色味の違いによって印象が変わるバリエーションもあります。
シンプルでありながら、幅広いイメージをつくりやすい点も、グレーならではの魅力といえるでしょう。
関連記事:こんな症状が出たら要チェック!チョーキング現象とはどんなことか徹底解説
周囲の景観になじみやすい
グレーは、周囲の建物や街並みに自然となじみやすい色です。
たとえば住宅地では、ベージュやブラウンなど落ち着いた色が多く見られますが、グレーはこれらの色調と自然に調和します。
目立ちすぎる色は個性として魅力的な反面、景観の中で浮いてしまうこともありますが、グレーは主張が強すぎず、視界の中に自然と溶け込むような存在感を持っています。
一見すると「個性がない」と感じるかもしれませんが、景観を乱さずに美しさを保つことも、ひとつの上質な個性といえるでしょう。
モダンで洗練された外観になる
外壁塗装の色選びでは、「モダンな印象にしたい」といった希望を耳にすることがよくあります。
モダンとは「現代的」「都会的」といった意味を持ち、シンプルで無駄のないデザインをイメージさせる言葉です。
グレーはそのモダンな印象を演出しやすい色として人気があります。
色味がなく、冷たすぎず温かすぎない中立的なトーンであることから、金属的でシャープな雰囲気を持つとされます。
これが無彩色ならではの魅力です。
反対に、木の質感や複雑な色合いを生かす「レトロ」な雰囲気とは異なり、グレーは無駄をそぎ落とした都会的な印象に仕上がります。
もちろん外壁材の質感にもよりますが、色をグレーにすることでシンプルモダンな外観に近づけることができるでしょう。
関連記事:【外壁塗装色の選び方】あなたの好みはなに色?ポイントを解説
グレーの外壁がもたらす印象の違い

グレーは白と黒の中間に位置する色で、外壁塗装でもよく選ばれる定番カラーです。
一見シンプルですが、濃淡や色味のわずかな違いによって、印象は大きく変わります。
この章では、グレーの持つ色のバリエーションや、外壁材やつやの違いによって変化する印象について解説します。
グレーの色味には幅がある
グレーといっても一色ではありません。
濃いグレーや薄いグレーだけでなく、青みがかった寒色系や赤みを帯びた暖色系など、わずかな違いで雰囲気が大きく変わります。
こうしたバリエーションが豊富なのは、グレーが他の色との親和性が高い色だからです。
ただし、メーカーによって同じ「グレー」でも色味に違いがあるため、イメージのすり合わせが難しいこともあります。
自分の思い描く色と施工後の色が異なるという失敗を防ぐためには、カラーシミュレーションの活用が有効です。
シンニッケンでは、こうした微妙な色のニュアンスまで再現できる高精度なシミュレーションをご用意しています。
外壁材との組み合わせで印象が変わる
グレーは中間色のため、単色で使うと印象が単調になりがちです。
しかし、外壁材の表面にある凹凸によって、光と影が生まれ、グレーに立体感をもたらすことができます。
たとえば、レンガ調の窯業系サイディングでは影が大きく出やすく、重厚感のある印象に。
一方、モルタル仕上げのように細かく不規則な凹凸を持つ外壁材では、やわらかく穏やかな印象に仕上がります。
このように、同じグレーでも下地となる素材の違いで雰囲気が大きく変わります。
シンニッケンでは、素材別の施工事例やデータも豊富に蓄積しているため、実例をもとに適した提案が可能です。
カラーシミュレーションと合わせてご活用ください。
つやの有無でも仕上がりが変化する
仕上がりの印象を左右する要素として、「つや(光沢)」も重要です。
つやがあると光を反射し、色が明るく見えやすくなります。
逆に、つやがないとマットで落ち着いた印象になり、色そのものがやや暗く見えることがあります。
ただし、「つやあり」「つやなし」という分類には明確な基準があるわけではなく、「半艶」や「控えめな光沢」など中間的な表現も使われます。
判断が難しいと感じる場合は、シミュレーションや実際の施工事例で比較してみると安心です。
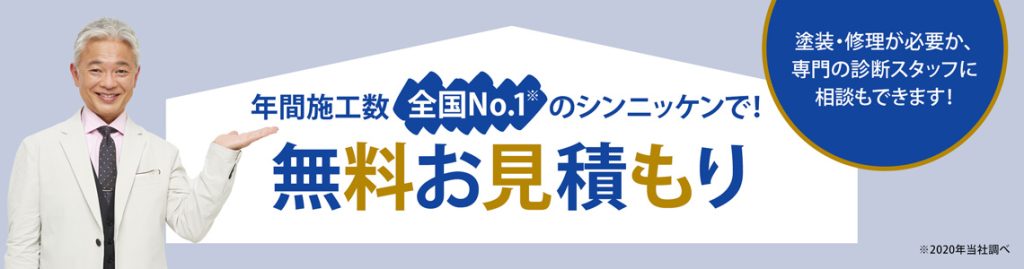
グレーを使った配色パターン

グレーは落ち着きのある色ですが、単体で使うとやや単調に感じられることもあります。
外壁材の質感や凹凸も印象を左右しますが、配色の工夫によって大きくイメージを変えることも可能です。
ここでは、単色・ツートン・アクセントカラーの使い方について解説します。
単色塗装で落ち着いた印象に
外壁塗装では、基本的に単色で仕上げるケースが多く見られます。
その理由は、屋根や外壁材の質感、玄関やサッシの色によって自然なアクセントが加わるため、配色を複雑にしなくても十分に変化を演出できるからです。
グレーは中間色のため、濃い色の屋根と組み合わせるとバランスによっては頭が重く見えることもあります。
全体の調和を考えた色選びが必要です。
また、単色にすれば使用する塗料の種類も少なくなり、コストを抑えるうえでもメリットがあります。
ツートン配色でメリハリを出す
ツートン配色とは、2種類の色を使って外壁に変化をつける手法です。
同じグレーでも明るさ(明度)に差をつけるだけで印象が大きく変わります。
ただし、色の組み合わせによってはちぐはぐな印象になることもあるため、全体の統一感や色の相性を意識することが大切です。
グレーの持つ落ち着きや汚れの目立ちにくさといった特性を活かした色選びを心がけましょう。
グレー×黒
黒とグレーの組み合わせは、重厚で落ち着いた印象を与えます。
特にスタイリッシュな雰囲気を出したい場合に効果的な配色です。
ただし、黒は視覚的に重く見えやすいため、外壁全体での使い方には注意が必要となります。
上部に黒を配置するとバランスが崩れて見えることがあるため、アクセントとして使うか、黒の使用面積を抑える工夫が効果的です。
グレー×白
グレーと白は相性がよく、すっきりと明るい印象を作る組み合わせです。
特に濃いグレーに白を合わせると、コントラストが生まれ、メリハリのある外観に仕上がります。
ただし、明るいグレーと白を組み合わせると、色の差が曖昧になり、ツートンの効果が薄れることがあります。
そのため、白をベースにグレーを差し色として使うような構成が一般的です。
白は汚れが目立ちやすいため、配置にも配慮が必要です。
グレー×ネイビー
ネイビーとグレーの組み合わせは、都会的で落ち着いた印象を与えます。
ネイビーが持つ深みが、グレーの中間色としての柔らかさを引き立て、飽きのこない配色となります。
ただし、ネイビーは黒に近い重さを持つため、使用する位置には注意が必要です。
上部にネイビーを使うと重たく感じることがあるため、建物の形や配分を考慮してバランスを整えましょう。
アクセントカラーで印象を引き締める
アクセントカラーは、外観に変化をつけるための「差し色」として活用されます。
玄関ドアや窓枠、ベランダの一部に異なる色を加えることで、全体のデザインにメリハリが生まれます。
単色塗装でも、実際にはサッシや玄関などの部材が異なる色で施工されることが多く、自然とアクセントが加わっているケースもあります。
ただし、大きく色を変えすぎると統一感を損なう原因にもなります。
目安としては、使用する色の数は3色以内に抑えるとまとまりのある印象になります。
グレーの持つ上品さや落ち着きを引き立てるためにも、アクセントは控えめにするのがポイントです。
カラーシミュレーションを活用すれば、全体のバランスを事前に確認できるため安心です。
グレーの外壁塗装でよくある失敗
グレーは人気のある外壁色ですが、選び方や組み合わせを間違えると、思っていた印象と違ってしまい「失敗した」と感じることもあります。
この章では、グレーの外壁塗装でよくある失敗例と、その原因について解説します。
イメージと違った仕上がりになる
グレーに限らず、外壁の色は完成後に「思っていた色と違う」と感じることがよくあります。
これは「面積効果」によるもので、小さな色見本で見た印象と、外壁のように広い面積に塗装したときの印象が異なるためです。
とくにグレーは、日光や照明の当たり方によって色が薄く見えやすく、つやの有無でも印象が変わってきます。
こうした失敗を避けるには、事前にカラーシミュレーションで仕上がりのイメージを確認することが重要です。
シンニッケンでは、こうした明度の変化も考慮した高精度なシミュレーションが可能です。
汚れが意外と目立つ場合がある
グレーは汚れが目立ちにくいと言われますが、選ぶ色味や質感によってはかえって汚れが目立つこともあります。
たとえば、明るすぎるグレーや、つやを抑えたマット仕上げは汚れが付きやすく、目立ちやすいです。
また、モルタル外壁のように細かな凹凸がある場合は、そこに土埃や排気ガスが溜まりやすく、見た目に影響します。
地域によって汚れやすさは異なるため、施工前に汚れ対策について相談しておくことが大切です。
他の家と差が出しづらくなることがある
グレーは人気の高い色のため、周囲の住宅と似たような色合いになる可能性があります。
街並みに自然と溶け込む反面、個性を出しにくいと感じる人もいるでしょう。
ただし、まったく同じ外観になるわけではありません。
グレーの色味を少し変える、差し色を加える、植栽でアクセントを加えるなど、工夫次第で印象に違いをつけることができます。
地味な印象になりやすい
中間色であるグレーは、落ち着いた雰囲気を演出できる一方で、派手さや華やかさには欠ける傾向があります。
そのため、選び方によっては「地味すぎる」と感じてしまうこともあるでしょう。
この場合は、少し色味を加えたグレーを選ぶのがおすすめです。
たとえば、青みのあるブルーグレー、赤みを含んだローズグレー、緑がかったモスグレーなどは、グレーの落ち着きを保ちつつ印象を和らげてくれます。
古びた印象を与える可能性がある
グレーの中でも、くすんだ色合いやつやのないマット仕上げを選ぶと、外観が古びたように見えてしまうことがあります。
表面に光沢がないことで、質感が失われやすくなるためです。
こうした印象を防ぐには、ほどよいつや感を持たせるのが有効です。
つやがあることで光を反射し、外壁に立体感や清潔感が生まれ、古びた印象を和らげることができます。
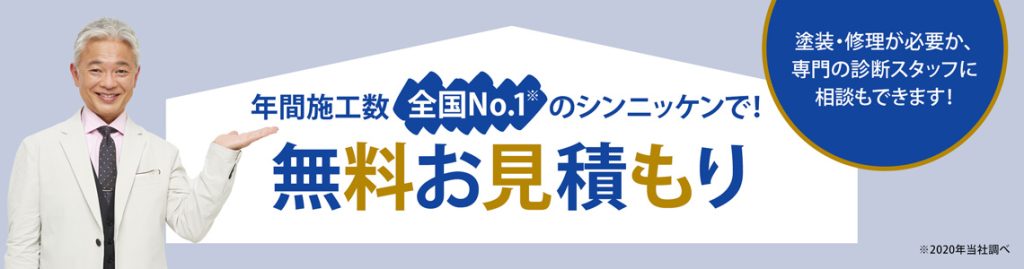
グレーの外壁塗装で失敗しないためのポイント

グレーの外壁は万能に思える一方で、色味の違いや周囲とのバランスを見誤ると、思わぬ失敗につながることもあります。
ここでは、グレーの外壁塗装を検討する際に押さえておきたいポイントを4つに分けて紹介します。
カラーシミュレーションで事前に確認する
外壁塗装では、完成後に「イメージと違う」と感じるケースも少なくありません。
特にグレーは、光の当たり方や周囲の環境で見え方が変わりやすいため、事前に仕上がりを確認することが大切です。
シンニッケンのカラーシミュレーションなら、写真をもとにしたリアルな完成イメージが確認できます。
色のトーンや質感の違いも反映されるため、実際の見た目に近い形で判断しやすくなります。
光の当たり方や立地環境を考慮する
グレーのような中間色は、光の加減によって見え方が大きく変化します。
たとえば、北向きの外壁は暗く見えがちで、思ったよりくすんだ印象になることもあります。
周囲の建物による影や、時間帯による光の変化も影響するため、立地に応じた色味の選定が必要です。
シミュレーションだけでなく、業者の施工事例を参考にしながら、自宅の環境に適した明るさ・色味を選ぶようにしましょう。
屋根・玄関・サッシとの色バランスを見ておく
外壁単体ではなく、建物全体としての配色バランスを見ることも重要です。
グレーはどの色ともなじみやすい反面、周囲の建材によって印象が左右される色でもあります。
特に濃い色の屋根と薄めのグレーを組み合わせると、バランスが崩れて見えることもあります。
サッシや玄関ドア、雨樋など、細部の色も含めて全体の調和を考えたうえで色を決めると、まとまりのある外観に仕上がります。
「なりたい印象」と「避けたい印象」を明確に伝える
外壁塗装の打ち合わせでは、「こうしたい」だけでなく「こうなってほしくない」という視点も伝えることが大切です。
「モダンにしたい」「明るくしたい」といった希望に加えて、「暗すぎるのは避けたい」「汚れが目立つのは困る」といった避けたい印象も具体的に言葉にすると、イメージの共有がスムーズになります。
言葉だけで伝えるのが難しい場合は、業者が持っている施工事例の写真などを見ながら相談すると、すれ違いも減らせるでしょう。
関連記事:オシャレな外壁塗装!?押さえておきたいポイントをご紹介
シンニッケンのカラーシミュレーションでグレーの外壁をイメージ
外壁塗装で最も重要なのは、「どんな色に仕上がるか」を施工前に正確にイメージできることです。
グレーと一口に言っても、明るさや色味によって印象は大きく変わります。
言葉だけではなかなかイメージを共有しにくいのが実際です。
たとえば、自分が思い描いているグレーが「明るいグレー」なのか「青みがかったグレー」なのかを、正確に言葉で伝えるのは難しいものです。
相手との認識にズレがあれば、仕上がりがイメージと異なるという事態にもつながりかねません。
そうした認識の違いを防ぐために役立つのが、シンニッケンのカラーシミュレーションです。
写真をもとに作成されるため再現性が高く、打ち合わせ時にも共通のイメージを持って話を進めやすくなります。
「思っていた色と違った」という後悔を防ぐためにも、シミュレーションを積極的に活用しましょう。
まとめ
外壁塗装においてグレーは、汚れの目立ちにくさや落ち着いた印象から、多くの人に選ばれている人気のカラーです。
ただし、同じグレーでも色味や素材、つやの違いによって仕上がりの印象は大きく変わるため、選び方には工夫が必要です。
配色のバランスや見え方の違いを把握しながら、自分の理想に近いイメージを明確にしておくことが、後悔しないためのポイントといえるでしょう。
シンニッケンのカラーシミュレーションを活用すれば、具体的なイメージを共有しながら安心して色選びが進められます。
納得のいく外壁塗装にするためにも、色の特性を理解したうえで、慎重に検討していきましょう。