プライマー塗装とは?塗装効果やシーラー・フィラーの違いを解説
最終更新 : 2025.07.27

外壁や屋根の塗装工事においては「プライマー塗装」という重要な工程があります。
しかし、専門的な知識がない一般の方にとっては難しい言葉で、不安に感じる方も少なくありません。
また、プライマーは「シーラー」や「フィラー」などと混同されやすく、それぞれの違いを正しく理解していないと、施工内容や見積もりを見た際に余計な不安や誤解を抱くことにもつながります。
そこで本記事では、プライマーの基本的な役割から、シーラー・フィラーとの違いまでをわかりやすく解説します。
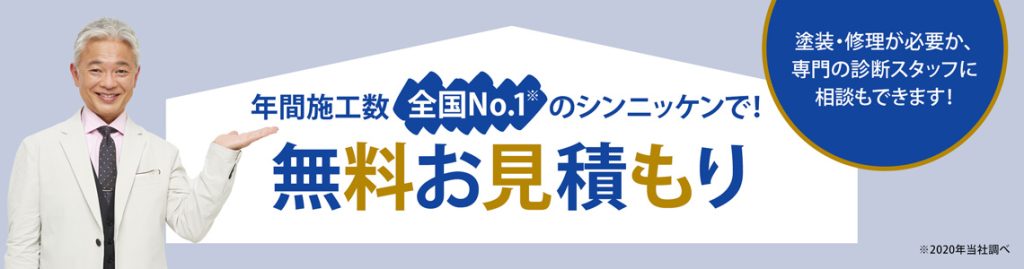
Contents
プライマー塗装とは?
プライマー塗装とは、外壁や屋根などの塗装における「下塗り」の工程を指します。
塗装と聞くと、外壁材や屋根材の上に直接色のついた塗料を塗るものだと思われがちですが、実は下塗り・中塗り・上塗りという3つの工程に分かれています。
プライマー塗装は中塗り塗料がしっかりと下地に密着するようにするために不可欠な工程であり、いわば塗装の接着剤のような役割を担っています。
なお、外壁材や屋根材には金属やモルタル、サイディングなどさまざまな種類があり、それぞれに合ったプライマー(下塗り塗料)を使うことで、塗料同士の密着性を高め、塗装の耐久性も向上します。
プライマーは透明または半透明であることがほとんどです。
色がつかないため見た目の変化は少ないものの、最終的な仕上がりや寿命に大きく影響するため、適切なプライマーを選定しなければなりません。
関連記事:外壁塗装の工事の流れとは?施工期間はどれくらいかかる?
プライマー塗装の役割と効果
プライマー塗装は具体的にどのような役割を果たし、どんな効果が得られるのかを詳しく解説します。
塗料の密着性向上
冒頭でもご紹介した通り、プライマー塗装の最大の役割は中塗り塗料と下地との密着力を高めることです。
これにより、塗料がはがれにくくなり、長期間にわたって美観や機能を保つことができます。
仮に、プライマー塗装をしないまま直接下地の上に塗料を塗ってしまうと、短期間で塗膜が浮いたり剥がれたりする恐れがあるため、接着の橋渡しとして重要な工程となります。
塗料の吸い込み防止
素材によっては塗料を吸い込みやすいものもあります。
たとえば、木材に直接塗料を塗ったとき、全体的に色が薄くなり木目が浮いて見えたという経験はないでしょうか。
プライマー塗装をせず下地の上に直接塗装するとこれと同じ現象が起こり、塗料の仕上がりにムラが出たり、塗料を無駄に消費したりする原因になります。
プライマー塗装には塗料の吸い込みを抑える効果もあり、塗装面を均一な状態に整えられます。
下地の調整効果
木材やモルタルなど、下地によっては微細な凹凸や傷があるものも存在します。
プライマーはこれらをカバーし、中塗り・上塗りの塗料が滑らかにのる状態に整える働きもあります。
特に古い外壁などでは、経年劣化によって細かなヒビやざらつきが見られる場合がありますが、適切なプライマーを使えば、そうした下地を補修しつつ塗装の精度を向上させることが可能です。
下地の色を目立たなくし発色を良くする
木材や金属など濃い色の下地の場合、塗料を塗っても下地の色が浮き出てしまい、思うような色にならないことがあります。
そこで、下地の上にプライマーを塗布することで発色が良くなり、塗料本来の色を再現できるメリットもあります。
サビ・腐食の発生を抑える
金属製の外壁材や屋根材は、下地に適切な処理を施しておかないとサビが発生し本来の性能を発揮できなくなります。
特に沿岸部の住宅では、海から吹き付ける潮風によってサビが発生しやすくなるため、防錆効果のあるプライマー塗装を施すことで塩害のリスクを低減できる可能性があります。
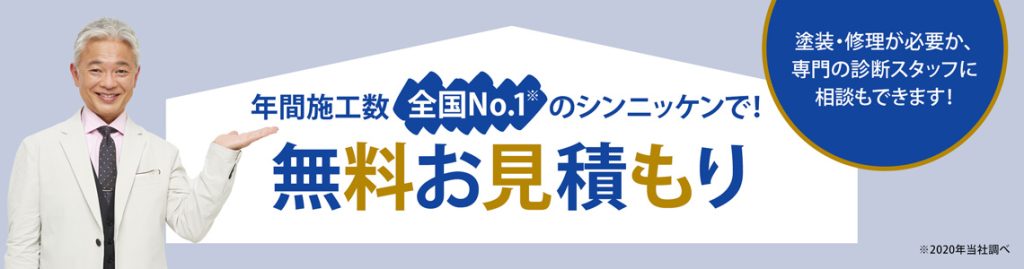
プライマー塗装に使われる主な種類と特徴
プライマーにはさまざまな種類があり、下地の材質や施工環境に応じて使い分ける必要があります。
ここでは、代表的な4つのプライマーについてその特徴と適した用途をご紹介します。
| 主な用途 | メリット | デメリット | |
| 水性プライマー | 多くの下地に対応する汎用タイプ | 臭いが少ない環境・人体への影響が少ない | 耐久性・密着性は低め乾燥に時間がかかる |
| 油性プライマー | 劣化した下地にも対応 | 耐久性・密着性が高い | 臭いが強い |
| 防錆プライマー | トタン屋根などの金属部材に使用 | サビや腐食を防ぐ | 水性タイプは乾燥に時間がかかる価格が高め |
| 導電性プライマー | 工場・研究所などの施設 | 帯電防止効果がある | 一般住宅向けではないためラインナップが少ない |
水性プライマー
水性プライマーはその名の通り、水を主成分としたプライマーです。取り扱いがしやすく臭いも少ないのが特徴です。
揮発性有機化合物(VOC)の排出量が少ないため環境や人体への影響を抑えられ、住宅地や学校などでも安心して使用できます。
モルタルやコンクリート、窯業系サイディングなど、多くの下地に対応できる汎用性の高いタイプです。
ただし、耐久性や密着性は油性プライマーに劣る場合があるほか、乾燥に時間がかかるというデメリットもあります。
油性プライマー
油性プライマーとは、溶剤(シンナー)を主成分としたプライマーです。
水性プライマーに比べると密着力と耐久性に優れており、劣化した下地や塗膜の強度が求められる箇所に適しています。
金属や古い塗膜面への塗装にも相性が良く、塗料の吸い込みをしっかり抑えたい場面でも効果を発揮します。
一方で、溶剤を使用していることもあり臭いが強いため、施工の際には換気や近隣への配慮が必要といったデメリットもあります。
防錆プライマー
防錆プライマーは、鉄などの金属下地に使われるサビの発生を防ぐ機能をもったプライマーです。
トタン屋根などの塗装前に使用されることが多く、錆びやすい場所に塗ることで長期間にわたって金属の腐食を防ぎます。
油性タイプが主流ですが、水性の防錆プライマーも登場しており、用途に応じて選択できます。
デメリットとしては、水性タイプは乾燥に時間を要するほか、防錆プライマーは全般的に価格が高めの傾向にあります。
導電性プライマー
導電性プライマーとは、電気を通す性質をもたせた特殊なプライマーです。
主に静電気の影響を受けやすい施設において、帯電防止を目的に用いられます。一般住宅ではあまり使われませんが、工場や研究施設など特殊な環境下では重要な役割を果たしています。
関連記事:外壁塗装には欠かせない下地処理とは?その効果と施工のポイント
プライマー塗装に適した製品を選ぶポイント

プライマーはどれを選んでも同じというわけではありません。
下地の種類や施工環境に合った製品を選ばないと、塗装がうまく密着しなかったり、早期に剥がれてしまったりする原因になります。
そこで、プライマーを選ぶ際に押さえておきたい基本的なポイントを3つ解説します。
1.下地の素材
プライマー選びでもっとも重要なのが、下地の種類に適した製品を選ぶことです。
たとえば、鉄やアルミといった金属系の下地に対しては、密着性に優れた油性プライマーや防錆プライマーが適しています。
一方、外壁材に使用されることの多いモルタルやコンクリート、窯業系サイディングには汎用性の高い水性プライマーが適しているでしょう。
素材によって塗料の密着具合や吸い込みが大きく異なるため、適合するプライマーを使うことが仕上がりと耐久性を左右します。
2.下地の状態
外壁や屋根の下地がどういった状態であるかもプライマー選びにおいて重要なポイントです。
たとえば、外壁の表面に白い粉が付着するチョーキングが見られる場合、劣化の程度は比較的軽いため水性プライマーでも問題なく施工できるでしょう。
一方、下地にひび割れが見られる場合には内部まで浸透し密着性を高められる油性プライマーが適しています。
3.塗装環境
屋外か屋内か、気温・湿度など、環境に応じた製品選びも重要なポイントです。
たとえば、屋内であれば臭いの少ない水性プライマーが適している一方、屋外では風雨や紫外線といった過酷な環境にさらされるため、耐久性に優れた油性プライマーや防錆プライマーを選ぶと長持ちしやすいでしょう。
また、公共施設や病院・学校などの場合には、環境負荷が低い低VOC製品が推奨されます。
4.施工のしやすさ
DIYでの塗装にチャレンジしたい方や、工期の短縮を最優先したい場合には施工性も重要なポイントです。
たとえば、水で希釈できる水性プライマーは初心者でも扱いやすいためDIYに適しています。
また、油性プライマーは乾燥時間が早いため、工期が限られている現場に最適なプライマーといえるでしょう。
用途や作業者のスキルに合わせて扱いやすい製品を選ぶことで、塗装面の仕上がり品質も安定しやすくなります。
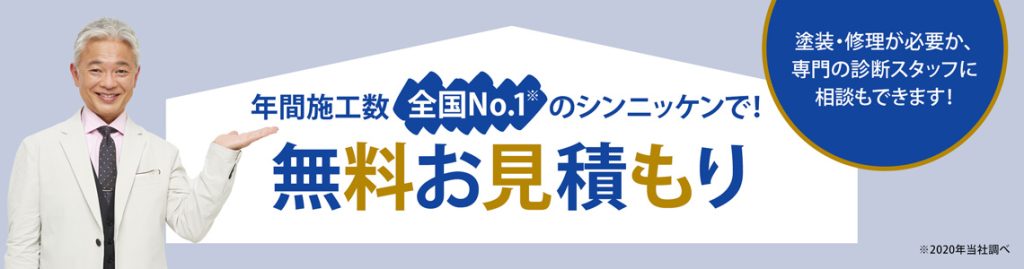
プライマー塗装とシーラー・フィラーの違い
下塗り材として使用されるのはプライマー以外にも、シーラーやフィラーといったものもあります。
これらはいずれも上塗り塗料の密着性を高めたり、下地を整える働きがあります。
塗装の品質や耐久性を向上させるためにも、それぞれの違いを正しく理解し使い分けましょう。
シーラーとは
シーラーは、主にモルタルやコンクリートなど、塗料の吸い込み量が多い下地に使用される下塗り材です。
シーラーを塗布すると下地の表面に薄い膜が形成され、塗料の吸収を防ぐことでムラのない仕上がりを実現します。
劣化した塗膜の密着性を高める効果もあるため、プライマーと同様に塗装面の接着剤としての役割を担います。
一般的にはシーラー=プライマーと認識されているケースが多く、製品によっては「プライマー兼シーラー」として販売されているものも少なくありません。
なお、シーラーには水性タイプと油性タイプがあり、劣化が見られる下地には油性タイプが多く用いられます。
フィラーとは
フィラーは、塗装面のわずかな凹凸や小さなひび割れを埋める目的で使用される下塗り材です。
塗布するとパテのような厚みが形成されるため、塗膜が薄いものがシーラー、厚いものがフィラーとよばれることも多くあります。
特にモルタルやALC(軽量気泡コンクリート)など、表面に粗さや劣化のある外壁にフィラーは多く使われます。
ただし、フィラー単体には密着性を高める効果が弱いため、シーラーやプライマーと併用されることが少なくありません。
フィラーには水性タイプが存在せず、油性タイプのみが販売されています。
関連記事:外壁塗装の塗料は何種類ある?選び方とおすすめの塗料ランキングを紹介
シンニッケンでは適切なプライマー塗装をご提案
外壁や屋根の塗り直しを行う際には、信頼できる専門業者に現地調査を行ってもらい、適切なプライマーの選定と施工を依頼することが重要です。
しかし、信頼性の高い専門業者の見極めは難しく、悪質な業者に依頼してしまうと想定外の追加料金が請求されたり、施工後に塗装の剥がれや浮きが目立ってくることも。
そのような不安を感じている方は、ぜひ一度シンニッケンへご相談ください。1990年から35年にわたって外壁・屋根の塗装を手掛けてきた歴史があり、これまで25万軒以上の施工実績を誇ります。
施工にあたっては丁寧な現地調査を行い、下地の状態に合わせたプライマーの選定と施工方法をご提案させていただきます。
また、シンニッケンでは全国に50拠点の支店・営業所を展開しているため、施工後のアフターフォローも万全。複数社の見積もりを比較する際には、ぜひシンニッケンもひとつの候補としてご検討ください。
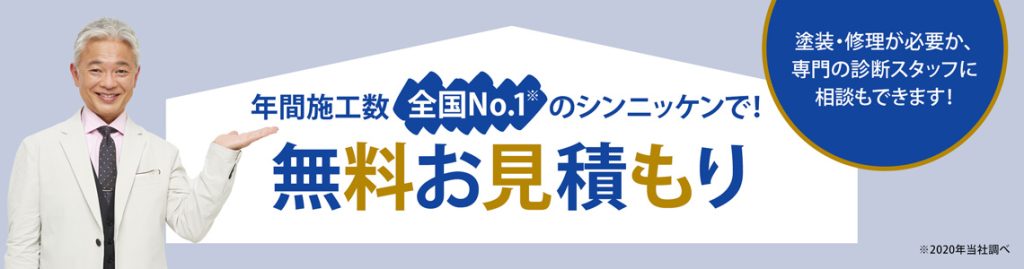
まとめ
塗装工事においてプライマー塗装は、単なる下準備ではなく塗料の密着性や耐久性を左右する重要な工程です。
プライマーの種類や役割を正しく理解することで、最終的な仕上がりや塗装の機能を最大限に引き出すことができます。
また、「シーラー」や「フィラー」といった他の下塗り材との違いも把握しておくことで、施工内容や見積もりに対する理解が深まり、業者とのやり取りにも安心感が生まれるでしょう。
塗装工事で失敗しないためにも、今回ご紹介した内容を参考にしながら、まずは信頼できる専門業者に相談・見積もりを依頼してみましょう。
